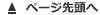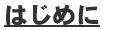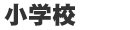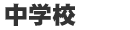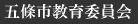垻懢彫妛峑
帠嬈幚巤曬崘彂
1.偼偠傔偵
杮峑偼丄帺慠偺宐傒朙偐側屲瀶巗偺拞偱傕丄摿偵椢朙偐側嶳乆偵埻傑傟丄媑栰愳偺旤偟偄棳傟偑恎嬤偱偁傞丅
偙偺傛偆側帺慠娐嫬偺拞丄彫婯柾峑乮慡峑帣摱俋侽柤乯偺椙偝傕惗偐偟丄巕偳傕偨偪偼妛擭偺榞傪偙偊偰拠椙偔妛峑惗妶傪憲偭偰偄傞丅
偦偙偱丄偙偺傛偆側摿怓傪惗偐偟丄傆傞偝偲偺帺慠偵栚傪岦偗丄抧堟偺曽乆傗儃儔儞僥矁A島巘摍偐傜妛傇偙偲傪捠偟偰丄帺暘偱壽戣傪尒偮偗丄
帺傜妛傃丄壽戣傪夝寛偟偰偄偙偆偲偡傞巕傪堢偰傞庢傝慻傒傪恑傔偰偒偨丅
偟偐偟丄帣摱堦恖傂偲傝偺婎慴妛椡傗惗妶廗姷幚懺挷嵏偺寢壥傪尒傞偲丄撉彂妶摦偵娭偟偰屄恖嵎偑戝偒偄偙偲偑柧傜偐偵側偭偨丅
撉彂偑岲偒側巕偼懡偄偑丄侾擔偺撉彂帪娫偼屄恖嵎偑戝偒偔丄壽戣偲側偭偰偄傞丅
2.撉彂妶摦悇恑偺偨傔偺庢傝慻傒
- 嘆丂慡峑堦惸偺撉彂妶摦偵偮偄偰
-
- 枅廡嬥梛擔乮俉丗俁侽乣俉丗係侽乯巒嬈慜偺侾侽暘娫丄慡峑堦惸撉彂傪峴偭偰偄傞丅
- 廡侾帪娫傪妛媺偺恾彂幒棙梡偺帪娫偲偟偰埵抲偯偗丄摿偵掅妛擭偼丄偙偺帪娫傪棙梡偟偰恾彂偺戄偟弌偟丒曉媝傪峴偭偰偄傞丅
- 崙岅壢偺庢傝慻傒偲偟偰丄奊杮偺撉傒暦偐偣傪捠偟偰曐堢強偲岎棳傪恾偭偰偄傞丅乮掅妛擭乽偍榖戭媫曋乿乯
- 妛廗帪娫傗梀曻帪側偳偵撉彂傪偟偨儁乕僕悢傪乽枅擔撉彂乿乮掅妛擭乯丄乽撉彂挋嬥乿乮崅妛擭乯偲偄偆僇乕僪偵婰榐偟丄堄梸傪崅傔偰偄傞丅

- 嘇丂恾彂埾堳夛妶摦偺妶惈壔
-
- 寧梛擔偐傜嬥梛擔偺嬈娫媥傒丒拫媥傒偵恾彂娰傪奐曻偟偰丄僐儞僺儏乕僞傪巊偭偰杮偺戄偟弌偟傪峴偭偰偄傞丅
- 乽偍榖攝払乿乽偍榖儚乕儖僪乿偲偄偆帪娫傪愝掕偟丄妛婜偵侾夞偢偮戝宆奊杮傗巻幣嫃傪撉傒暦偐偣偡傞妶摦傪峴偭偰偄傞丅 杮偺慖掕傗挬夛偱偺屇傃偐偗傕帣摱偑峴偭偰偄傞丅
- 乽壞媥傒撉彂僇儗儞僟乕乿乽搤媥傒撉彂僇儗儞僟乕乿傪嶌惉偟丄挿婜偺媥傒拞偺撉彂偺廩幚偵栶棫偰偰偄傞
- 乽幍梉廤夛乿偱幍梉偵傑偮傢傞寑傗僋僀僘傪婇夋偟丄偟偍傝傪慡峑帣摱偵僾儗僛儞僩偟偨丅
- 廐偺撉彂廡娫偵偼丄乽撉彂偺栘乿偺庢傝慻傒傪峴偭偰偄傞丅帣摱偑栘偺梩宆偺僇乕僪偵偍偡偡傔偺杮偺戣柤傪彂偒丄偦偺梩偭傁偑偳傫偳傫憹偊傞傛偆偵屇傃偐偗偨丅
- 僐儞僺儏乕僞偱懡撉幰傪挷傋丄庤嶌傝偺徿忬傪嶌惉偟丄挬夛側偳偱昞彶傪峴偭偨
- 嘊丂娐嫬惍旛
-
- 恾彂偺峸擖傪擭俀夞偵暘偗偰峴偄丄帣摱偺儕僋僄僗僩杮傗榖戣惈偺偁傞杮傪峸擖偟偰偄傞丅
- 怴偟偄杮偺徯夘僐乕僫乕傪愝掕偟丄杮偵懳偡傞娭怱傪崅傔傞傛偆偵偟偨丅
3.恾彂娰巟墖堳偺妶摦偵偮偄偰
- 嘆丂妛峑恾彂娰偺塣塩偵岦偗偨巟墖
-
- 枅廡嬥梛擔丄係帪娫乮侾侽帪乣侾係帪乯偺巟墖傪峴偭偨丅
- 妛媺偺恾彂幒棙梡偺帪娫偵恾彂偺慖掕偺傾僪僶僀僗傗戄偟弌偟丒曉媝傪峴偭偨丅
- 乽憤崌揑側妛廗偺帪娫乿傗崙岅壢丒惗妶壢摍偱偼丄僥乕儅偵増偭偨恾彂偺慖掕偺傾僪僶僀僗傪峴偭偨丅
- 恾彂偺暘椶昞帵丄憼彂揰専丄杮偲彂壦偺暲傃懼偊丄憼彂偺廋棟側偳恾彂娗棟傪悘帪峴偭偨丅

- 嘇丂恾彂埾堳夛妶摦偺妶惈壔偵偮側偑傞巟墖
-
- 嬥梛擔偺嬈娫媥傒丒拫媥傒偵杮偺戄偟弌偟摍偺僒億乕僩傪峴偭偨丅
- 乽偍榖攝払乿乽偍榖儚乕儖僪乿偺撉傒暦偐偣楙廗偺僒億乕僩傪峴偭偨丅
- 乽壞媥傒撉彂僇儗儞僟乕乿乽搤媥傒撉彂僇儗儞僟乕乿傪宖帵偟丄僐儊儞僩傪彂偄偨丅
- 乽幍梉廤夛乿偱偼幍梉偵傑偮傢傞岅傝暦偐偣傪峴偭偨丅
- 廐偺撉彂廡娫偵偼丄乽偍偡偡傔偺杮乿傪徯夘偟乽撉彂偺栘乿偺弨旛傪峴偭偨丅
- 嘊丂妛峑恾彂娰偺娐嫬惍旛偵岦偗偨巟墖
-
- 婫愡姶偁傆傟傞宖帵暔傪嶌惉偟丄恾彂娰慜偺宖帵斅傪忺偭偨丅
- 恾彂娰撪偺宖帵斅偵偼丄枅寧怱偵巆傞帊傪徯夘偟偨丅
- 怴偟偄杮偺徯夘僐乕僫乕傗僥乕儅暿偺徯夘僐乕僫乕傪愝掕偟丄杮偵懳偡傞娭怱傪崅傔偨丅
- 嘋丂妛峑恾彂娰娫偺楢実偵岦偗偨巟墖
-
- 屲瀶巗偺恾彂娰僱僢僩儚乕僋偺庢傝慻傒偺堦偮偱偁傞乽暔岅掕婜曋乿偺庴偗擖傟張棟傪峴偄丄戄偟弌偟側偳傪峴偭偨丅
- 乽憤崌揑側妛廗偺帪娫乿傗崙岅偺嫵嵽偵娭傢傞恾彂偺慖掕傪屲瀶巗棫恾彂娰偲楢実偟偰丄偦傠偊偰偄偭偨丅
4.惉壥偲壽戣
奺峑偵巌彂嫵桜偑攝抲偝傟丄妛峑恾彂娰傪妶梡偟偨嫵堢妶摦傗撉彂妶摦偺拞怱揑栶妱傪扴偆偙偲偑媮傔傜傟偰偄傞丅 偲偙傠偑丄妛媺扴擟偲偟偰偺巇帠傗峑柋暘彾偺攝暘側偳偐傜丄巌彂嫵桜偲偟偰偺嬈柋偵愱擮偱偒側偄偺偑尰忬偱偁傞丅 幚嵺偵偼丄恾彂偺慖掕丒廂廤丒憰旛傗憰挌偺廋棟丄恾彂偺娗棟丄恾彂埾堳夛偺巜摫偱惛堦攖偱偁傞丅
偙偆偟偨拞偱丄妛峑恾彂娰巟墖堳偵丄恾彂娰偺塣塩偵娭偡傞巟墖傪峴偭偰捀偄偨偙偲偼丄巕偳傕偨偪偺撉彂妶摦偺悇恑偵偍偍偄偵栶棫偭偨丅
巕偳傕偨偪偑撉彂偵恊偟傓婡夛偺採嫙偲娐嫬偺惍旛偑恑傔傜傟偨偙偲偼丄戝偒側惉壥偱偁偭偨丅
傑偨丄奊杮偺撉傒暦偐偣乮掅妛擭乯傗僽僢僋僩乕僋乮崅妛擭乯側偳傪峴偭偰傕傜偭偨偙偲偱丄嫵巘偺尋廋偵傕側偭偨丅
堦曽丄廡堦夞偺尷傜傟偨帪娫撪偺妶摦側偺偱丄巌彂嫵桜偲巟墖堳偲偺楢実偑庢傝偯傜偄応崌偑懡偄丅
偦偙偱亀恾彂幒楢棈僲乕僩亁傪嶌惉偟丄巟墖偟偰傎偟偄撪梕傗巕偳傕偨偪偺條巕側偳傪偮偯偭偰偄偭偨偑丄
偦傟偵傛偭偰偍屳偄偺僐儈儏僯働乕僔儑儞偑僗儉乕僘偵恾傟傞傛偆偵側偭偨丅
壽戣偲偟偰偼丄巟墖擔傪憹傗偟丄傛傝堦憌撉彂妶摦偺悇恑傪恾傟偨傜偲巚偆丅