|
HOME >
学校要覧 > 大塔中学校 |
 |
|
大塔中学校要覧 (平成23年度) |
| |
|
1.教育目標
(1)教育目標
|
| |
「ふるさとを愛し,輝く瞳で学び、力強く未来をきりひらく子どもの育成
」
−知性と理性を磨き、人間味あふれる豊かな心とたくましい体を持って、力強く生きる生徒の育成− |
|
(2)学校経営の方針 |
| |
「基礎・基本の定着を図り、個性と創造性を大切にする学校」
「命と人権を大切にする学校」
「保護者や地域住民に信頼される学校」 |
|
(3)めざす生徒像 |
| |
(ア)意欲的に学び、健康で安全な生活を送る生徒
(イ)お互いの人権を守り、仲間と協力し合える生徒
(ウ)人を愛し、ふるさとを愛し、学校を愛する生徒
|
|
(4)学校教育目標を達成するための基本方針 |
| |
○ 教育の基本方針に基づく教育活動を推進し、新しい文化の創造に努める人間を育成する。
○ 小学校と中学校のそれぞれの良さを生かしながら、小中学校の教職員が一体となって
9年間の連続性・継続性を重視した教育を推進する。
○ 創意ある楽しい学校づくりを推進する。
○ 個と集団が生きる授業づくりに努める。
○ 自主性と豊かな心を育てる活動づくりを推進する。
|
| |
|
|
|
2.学校の沿革
|
| |
昭和22年
|
4月
|
学校改革により新制中学校創設
、開校式挙行
本校を辻堂小学校に、分校を惣谷小学校におく |
| |
昭和30年 |
6月 |
惣谷分校独立により、大塔第一中学校と改称 |
| |
昭和31年 |
9月 |
新校舎落成(校舎本館及び体育館) |
| |
昭和32年 |
11月 |
プール竣工(25m) |
| |
昭和33年
|
8月
11月 |
学校林を設置(宇井カカツル86の1)
校歌制定 |
| |
昭和34年 |
8月 |
「産業教育研究校」の指定校となる |
| |
昭和35年 |
11月 |
文部省指定「産業教育」研究発表 |
| |
昭和36年 |
4月 |
制服制定 |
| |
昭和38年 |
8月 |
給食場竣工 |
| |
昭和44年 |
3月 |
統合により大塔中学校第1校舎となる |
| |
昭和45年 |
4月 |
実質統合、大塔中学校開校式 |
| |
昭和46年 |
1月 |
寄宿舎(柏葉寮)開設、柏葉寮入寮式 |
| |
|
10月 |
学校環境緑化コンクール入賞 |
| |
昭和47年 |
2月 |
職員宿舎8戸完成 |
| |
|
11月 |
健康優良学校特選校 |
| |
昭和49年 |
10月 |
村民体育館落成 |
| |
昭和52年 |
3月 |
職員宿舎(2戸建1棟) |
| |
昭和58年 |
10月 |
第27回奈良県へき地教育研究大会で研究発表 |
| |
昭和60年 |
3月 |
寄宿舎(柏葉寮)閉鎖 |
| |
昭和61年 |
4月 |
「勤労生産学習研究校」の指定校となる |
| |
昭和62年 |
11月 |
「勤労生産学習」研究発表 |
| |
平成4年 |
5月 |
「勤労生産学習研究校」の指定校となる |
| |
平成5年 |
10月 |
第37回奈良県へき地教育研究大会で研究発表 |
| |
平成9年 |
4月 |
「豊かな心を育む教育実践研究協力校」の指定校となる |
| |
平成10年 |
11月 |
「豊かな心を育む教育実践」研究発表 |
| |
平成14年 |
10月 |
第46回奈良県へき地教育研究大会で研究発表 |
| |
平成15年 |
3月 |
校舎新築に伴い仮校舎へ移転 |
| |
平成16年 |
9月 |
大塔小中学校新築、体育館改修工事竣工 |
| |
平成17年 |
9月 |
五條市との合併により五條市立大塔中学校となる |
| |
平成18年 |
7月 |
大塔小中プール竣工。 |
| |
平成19年 |
10月 |
第56回全国へき地教育研究大会で研究発表。 |
|
平成21年 |
10月 |
第53回奈良県へき地教育研究大会で研究発表 |
|
平成22年 |
10月 |
奈良県人権教育研究大会全体会で記念行事発表 |
|
3.生徒数
(平成23年4月1日現在) |
|
|
1年 |
2年 |
3年 |
計 |
|
学級数 |
1 |
1 |
1 |
3 |
|
生徒数 |
1 |
0 |
4 |
5 |
|
| |
| 4.校歌 |
| |
|
|
|
| |
|
|
作詞:西尾芳喬/作曲:柳川辰雄 |
|
|
|
1
|
歴史(ふみ)香る 峰の若葉よ
豊かなる 光を浴びて
たゆみなく 力を伸ばす
たくましき 若人われら
栄えあれ 大塔中学 |
2
|
大塔湖(みずうみ)の 深き眸よ
いと遠き星を めざして
あけくれに 心を磨く
輝けき 若人われら
誉れあれ 大塔中学 |
|
|
|
| |
| 5.校章 |
| |
|
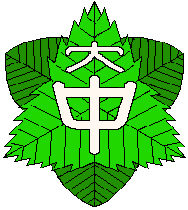 |
| |
|
三葉の柏と三枝の松(杉という説も?)を重ね、その上に「大中」の文字が浮かび上がる。柏の葉は、旧大塔村の村名の由来にもなっている大塔宮護良親王所縁の木と伝え聞く。奈良学芸大学(現奈良教育大学)阪本一男教授製作による。 |
|
|
| |

